
はじめに:子どもを守る防犯、何から教える?
「知らない人についていっちゃダメ!」
この言葉、誰しも一度は子どもに言ったことがあると思います。
でも、元警察官として現場を見てきた立場から言わせてもらうと、それだけじゃ不十分なんです。
実際に起きた事件の中には、「何度か見たことある人だった」「怖くて動けなかった」というケースがたくさんあります。
子ども自身が“自分の身を守る力”を少しずつ身につけていけるように、親ができるサポートがあります。
そこで今回は、警察官として10年間、いろんな現場を見てきた僕が「これだけは今すぐ、子どもに本当に教えておいてほしい!」と思う防犯の基本を、5つのルールにまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください!
結論!子どもに教えるべき防犯5か条
- 知らない人に話しかけられたら、すぐにその場から離れる(練習しておく)
- 人の少ない・死角の多い場所では遊ばない
- 防犯ブザーは持つだけじゃなく、“鳴らす練習”をしておく
- 困ったときに“誰に助けを求めるか”を具体的に教えておく
- 不審者情報や通報は親の役目。子どもが安心できる環境を整える
この5つが、子どもの命を守る基本になります。
それぞれ、どんなことを意識すればいいか、次から詳しく解説します。
第1条:「知らない人に“話しかけられたら”どうするか」を練習しておく
「知らない人についていっちゃダメ」だけではなく、**“話しかけられた瞬間の対応”**を教えておくことが大切です。
子どもにとって「知らない人」は意外とあいまい。
名前を呼ばれたら“知り合い”と勘違いしたり、「ママの友達」と言われると信用してしまうことも。
大切なのは、“距離をとること”と“逃げること”を迷わずできるようにしておくこと。
親子で実際にロールプレイ(ごっこ遊び)をしながら、「どんな時に逃げる?」「どうやって逃げる?」を練習しておくのがおすすめです。
第2条:遊ぶ場所の“危険サイン”を親子で話す
事件やトラブルが起きやすい場所には、ある共通点があります。
- 人気が少ない
- 死角が多い(フェンス・植え込みなど)
- 近くに助けを求める場所がない
こういった場所を“事前に一緒にチェックしておく”ことで、子ども自身も自然と警戒心が育ちます。
「ここの公園はちょっと暗いね」
「この道、人が少ないから1人の時はやめようか」
といった会話を普段からするだけでも、立派な防犯教育になります。
第3条:防犯ブザーは“持たせるだけ”じゃ意味がない
防犯ブザーをランドセルにつけて安心していませんか?
実は、とっさに鳴らせない子は意外と多いんです。
特に、ブザーの位置がランドセルの下の方だったり、コードが絡んでいたりすると、実際の場面で役に立たないことも。
- 一度、実際に鳴らしてみる(音に慣れさせる)
- どこにつけるのがいいか、一緒に考える
- 「変な人が来たら鳴らしていいんだよ」と伝えておく
ブザーを鳴らす=悪いこと、恥ずかしいこと、という思い込みを消すことも大切です。

第4条:「助けて」が言えない子に、“誰にどう助けを求めるか”を教える
いざというときに、「助けて」と言えない子は多いです。
怖かったり、混乱していたり、自信がなかったり。大人だってそうです。
だからこそ、
- **「どんな人に助けを求めていいか」**を明確にしておく
- **「どう声をかければいいか」**を練習しておく
のがポイントです。
たとえば、「近くのお店の人」「制服を着た人(警察官・駅員・警備員など)」「子どもを連れた女性」など、“「助けて」と言いやすい相手”のイメージを事前に決めておくと、いざという時に行動しやすくなります。
第5条:通報は“親の仕事”。不審者情報を見たらどう動くか決めておく
最近は自治体のサイトや防犯アプリなどで「不審者情報」がチェックできます。
でも、ただサイトを見て終わりではもったいない。
- 情報を見たら「いつ(何時何分)」「どこで」「どんな人だったか」を子どもと共有
- 帰り道や遊ぶ時間を少し調整する(各地域の不審者情報が多い時間を避けるなど)
- 「迷ったらすぐ警察に通報していい」ことを家族で共有する
また、子どもが「なんか怖かった」「変な人いたかも」と感じたら、親がすぐ対応する姿を見せることも防犯の一環になります。
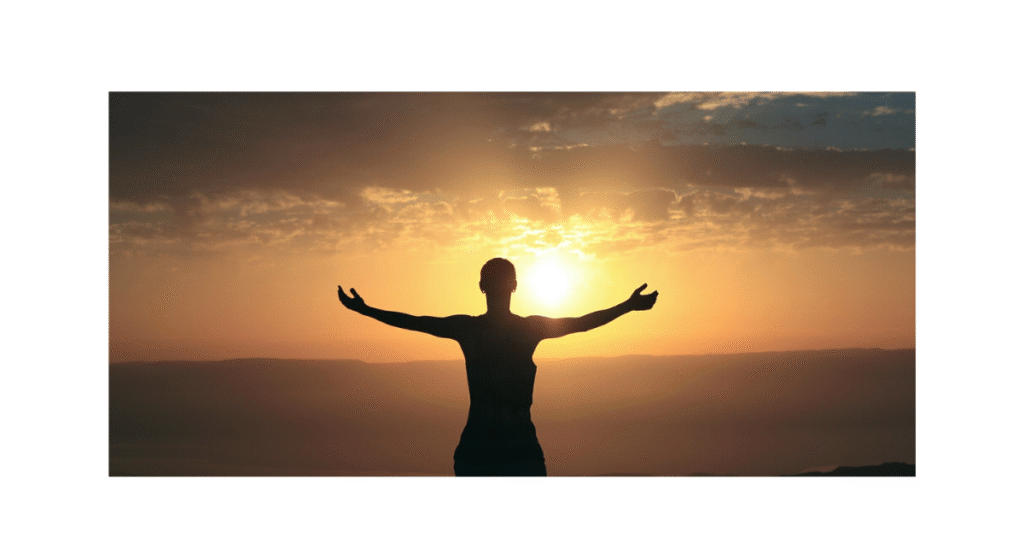
🔚 おわりに:防犯は、日常の中に“ちょっとだけ”でいい
子どもにとって、日常の中で「安心できる力」を育てることが、一番の防犯になります。
大切なのは、怖がらせることではなく、「知っていれば安心できる」ことを伝えること。
この5か条を、ぜひ今日から少しずつ、お子さんと話してみてください。
特別な訓練じゃなくていいんです。
お散歩しながら、お風呂で、寝る前にちょっとだけ。
元警察官として、そして今は2児の父として、
「子どもが無事に帰ってくること」こそが、親の一番の願いだと思っています。
Proudly powered by WordPress
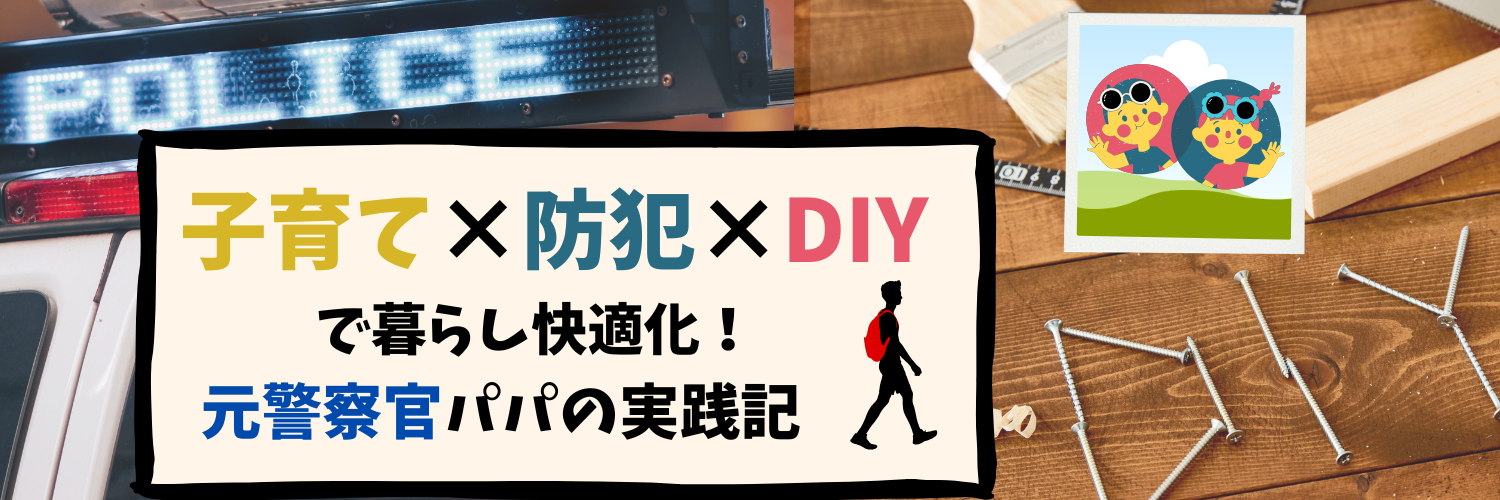



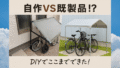
コメント