はじめに
電子決済、サブスク、リモートワーク、そしてAI——
世の中はここ数年で驚くほど進化しています。きっと子育て中のパパママなら、一度はこう考えたことがあるはずです。
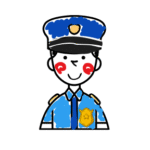
「この先、子どもたちはどんな社会で生きていくんだろう…?」
そんな疑問に答えてくれたのが、元小学校校長・教育の第一線で活躍し続ける松田 孝先生。
プログラミング教育のパイオニアでもある松田先生に子どもの未来と教育についてたっぷり伺ってきました!
松田 孝さん プロフィール
- MAZDA Incredible Lab 代表
- 教育現場に約40年/校長歴13年
- 総務省・文部科学省などの各種委員も歴任
- 金沢市プログラミング教育ディレクター
- 著書『学校を変えた最強のプログラミング教育』など多数
| 学校を変えた最強のプログラミング教育 [ 松田孝 ] 価格:1,760円(税込、送料無料) (2025/7/7時点) 楽天で購入 |
子どもたちの20年後は、どんな世界?
まず松田先生が語ってくれたのは「時代の流れと社会の変化」。
通信技術の進化と社会の変化
- 1995年:ダイヤルアップ(Society3.0)
- 2000年代:3G(モバイル通信の本格始動)
- 2012年:LTE/4Gでネット環境が大きく変わる
- 2025年:5G、AI、IoTが浸透中(Society5.0)
- 2035年:6G
- 2045年:7G、そして量子テクノロジーの時代へ?
松田先生はこのような未来社会を「Society6.0」と表現しています。
これはAI、量子コンピュータ、仮想空間が深く関わる新しい人間社会のあり方です。
これからの子どもに必要な「3つの力」
① 非認知能力:自分と向き合い、他者とつながる力
自分と向き合う力
- 自制心
- 忍耐力
- 回復力(レジリエンス)
自分を高める力
- 意欲・向上心
- 自信・自尊感情
- 楽観性
他者とつながる力
- 共感性
- 社会性
- コミュニケーション能力
② コンピュータサイエンス:AI時代の必須知識
もはやITと無縁で生きることは不可能な時代。
だからこそ、コンピュータサイエンスの基礎は全ての子どもにとって必要な素養になります。
プログラミング教育は、その最適な入口。
なぜプログラミングなのか?
- 試行錯誤する力
- 問題を構造的に捉える力
- 機械を「正しく使う」ためのリテラシー
その中でも注目すべきは「ハルシネーション」への対応です。
💡 ハルシネーションとは?
AIがもっともらしい“ウソ”を出力する現象のこと。
ChatGPTなどの生成AIが、事実でないことを堂々と述べてしまう例もあります。
これからの社会では、「情報を疑い、自分の頭で考える力」が不可欠。
その土台作りに、プログラミング的思考が役立つのです。
③ 身体性の練磨:人間らしさを育む経験
「人間としての幸せは、五感を豊かにすること。AIには“身体”がない。
だからこそ、自分の限界に挑戦する経験こそが、人間である証明になる」
- スポーツ
- 外遊び
- 手仕事・創作活動
こうした体験が、これからの時代にも欠かせない「生きる力」となるのです。
親ができることは?
- 一緒にプログラミング体験をしてみる
- 新しい技術に「わからない」と言わずに楽しむ姿を見せる
- 外遊び・身体活動もバランスよく取り入れる
まとめ
AI・量子技術・6Gが進化する未来社会。
その中で、子どもたちに求められるのはこの3つの力です:
- 非認知能力(=自己肯定感の土台)
- コンピュータサイエンス(=ITリテラシー)
- 身体性の練磨(=人間らしさ)
そして何より、親が一緒に学び、楽しむ姿勢こそが最高の教育になるのかもしれません。
補足:Society5.0とは?
「Society5.0」とは、AIやIoTを活用し、経済成長と社会課題の解決を両立する超スマート社会のこと。
狩猟 → 農耕 → 工業 → 情報 → そして第5の社会へ。
Proudly powered by WordPress
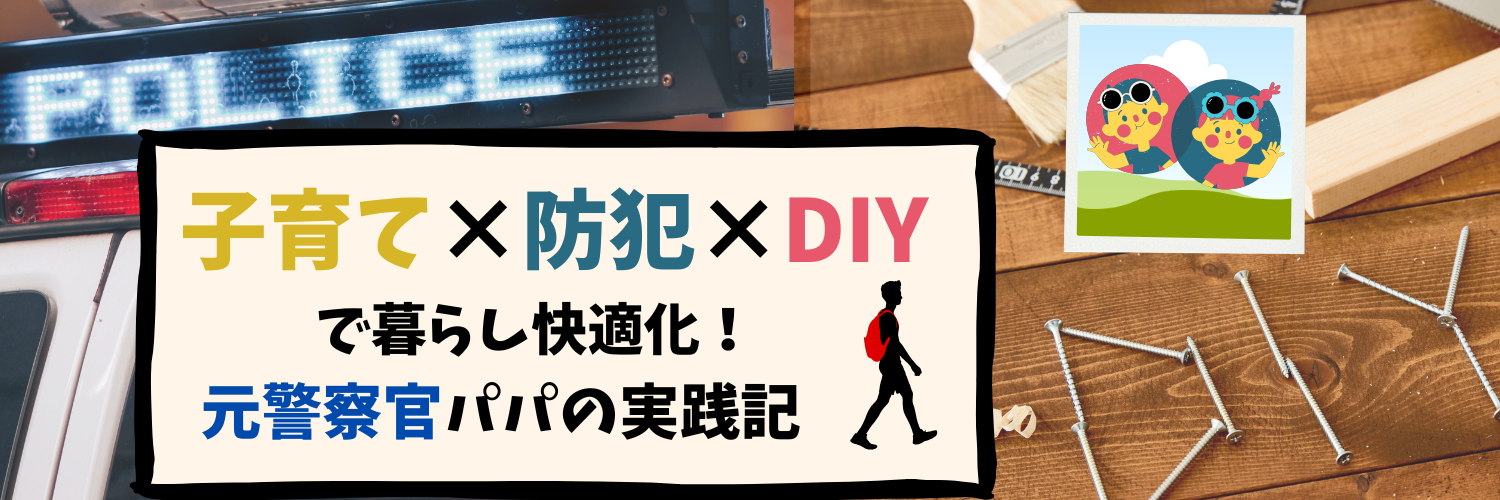
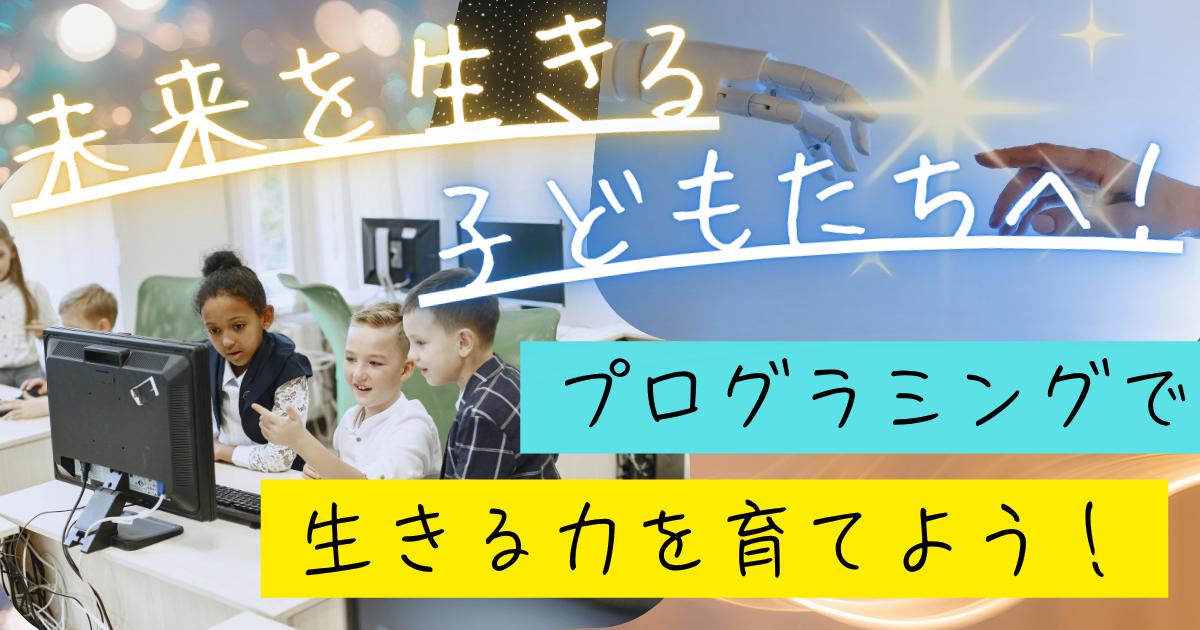

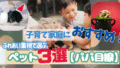
コメント